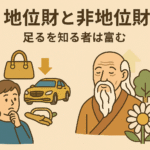- はじめに:満たされているのに虚しい理由
- 老子の『足るを知る者は富める』とは?
- 資産が増えると物欲がなくなる本当の理由
- 心が満たされる豊かさとは?
- FIREと知足の関係性
- 虚しさをどう受け止めるか?
- おわりに:自分なりの“足る”を見つけよう
はじめに:満たされているのに虚しい理由
最近、資産が増えてきたことで物欲が不思議と減ってきた。
昔はイオンモールに行けばあれもこれも欲しくなって、雑貨を見て、服を手に取って、あれこれ悩むのが楽しかった。
けれど今は、映画を見てご飯を食べたら「もう帰ろうかな」と感じるようになった。
財布には余裕があるし、欲しい物を買えないわけじゃない。なのに、心が踊らない。
満たされているはずなのに、どこか少しだけ虚しい。そんな気持ちに、心当たりがある人は少なくないはずだ。
老子の『足るを知る者は富める』とは?
この感覚に、ヒントをくれる古い言葉がある。
それが、古代中国の哲学者・老子の残した「足るを知る者は富める」という言葉だ。
原文では『知足者富』。『道徳経』第33章に出てくる一節だ。
知足者富(足るを知る者は富めり)
──『老子(道徳経)』第33章
意味は「満足することを知っている人こそ、真に豊かである」というもの。
物や金をどれだけ持っていても、満足できない人は決して心から満たされることはない。
逆に、今あるものに感謝し、そこに価値を見出せる人は、すでに豊かであると老子は説いている。
資産が増えると物欲がなくなる本当の理由
物欲がなくなる現象には、ちゃんとした理由がある。
それは「足りない状態」が解消されるからだ。
欲というのは本来、「足りない」「欠けている」と感じることで生まれる。
収入が少なかった頃は、「あれが欲しい」「これが手に入ったら幸せ」という“欠乏感”がモチベーションだった。
でも資産がある程度増えてくると、「欲しいものはだいたい買える」という状態になる。
その瞬間、「買えないことによる欲望」ではなく、「買えるけど買わない」という選択が当たり前になる。
すると、物を買うこと自体にドキドキしなくなる。
買い物が娯楽だった頃のワクワク感は、いつの間にかどこかへ消えてしまう。
そして気づく。「あれ?買いたいもの、特にないな」と。
心が満たされる豊かさとは?
ここで重要なのは、「満足=退屈」ではないということ。
実は、“物欲がなくなる”というのは、単なる無気力ではなく、価値観のシフトだ。
つまり、「所有すること」よりも「体験すること」「成長すること」「心を動かすこと」へと重心が移っている。
たとえば旅行。動画で見た絶景を実際にこの目で見てみたい。
誰かと話しながら温泉に入ったり、静かな朝に海辺を歩いたり、そういう体験は物以上に記憶に残る。
モノでは得られない、深い満足感がある。
お金を使う対象が、「物を得る」から「心を動かす」へと変わってきているのかもしれない。
FIREと知足の関係性
FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指している人にとって、
「足るを知る」はまさに核となる価値観だ。
働かずに生きるには、収入を増やすだけでなく、支出を抑える=欲を見直すことが不可欠だからだ。
投資や節約を続けて資産が貯まると、自然と「本当に必要なものは何か?」と考えるようになる。
その結果、モノに執着しなくなり、「なくても大丈夫な物」が増える。
そして次第に、生活のシンプルさや時間の自由さに喜びを感じるようになる。
これはまさに、老子の言う「知足者富(足るを知る者は富める)」の実践そのものだ。
虚しさをどう受け止めるか?
物欲が消えていく過程で、たしかに寂しさや虚しさを感じる瞬間はある。
それは「目標がなくなった」ように感じるからかもしれない。
これまで“欲しい物を手に入れること”が一種の生きがいだったのなら、その拠り所がなくなるのは当然のことだ。
でもこれは悪いことではない。
むしろ、「次のフェーズに進む時期が来た」ことのサインともいえる。
物で満たされる段階から、
体験、人とのつながり、内面の成長、人生の質そのものを大切にする段階へ。
FIRE後に自由な時間が生まれたら、今感じているこの空白も、豊かに埋めていけるはずだ。
おわりに:自分なりの“足る”を見つけよう
老子の言葉は、数千年を超えて現代にも通じる。
とくに、お金がある程度あるのに虚しさを感じる今のような時代には、ひときわ心に響く。
FIREを目指す人、節約している人、あるいはすでに物欲が消えて困惑している人へ。
「足るを知る者は富める」という言葉は、きっと何かのヒントになるはずだ。
すでに“富んでいる”と気づくこと。
それこそが、本当の豊かさなのかもしれない。
足るを知る者は、すでに富んでいる。